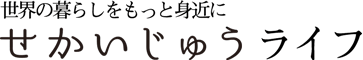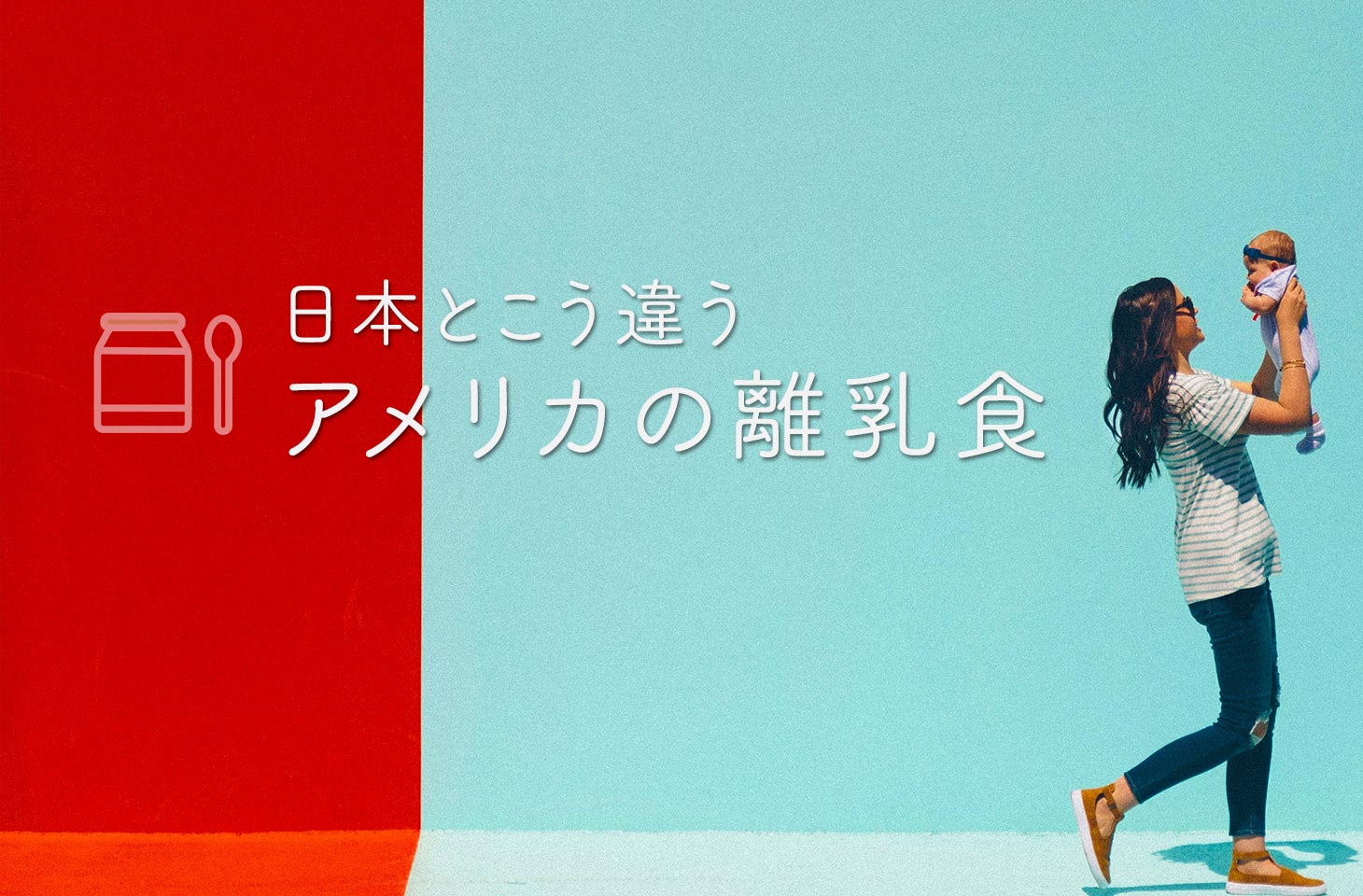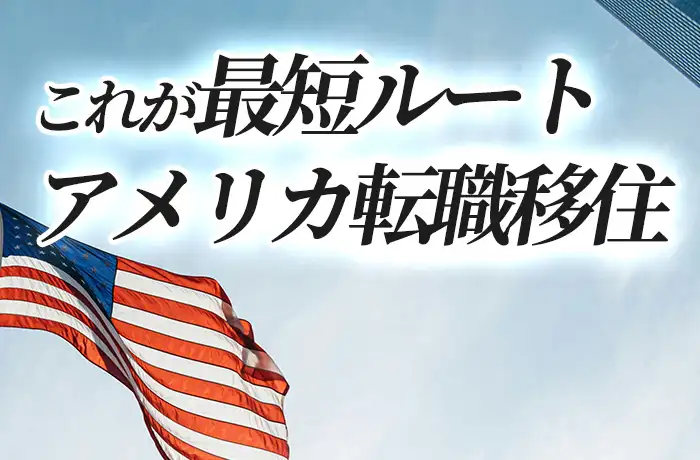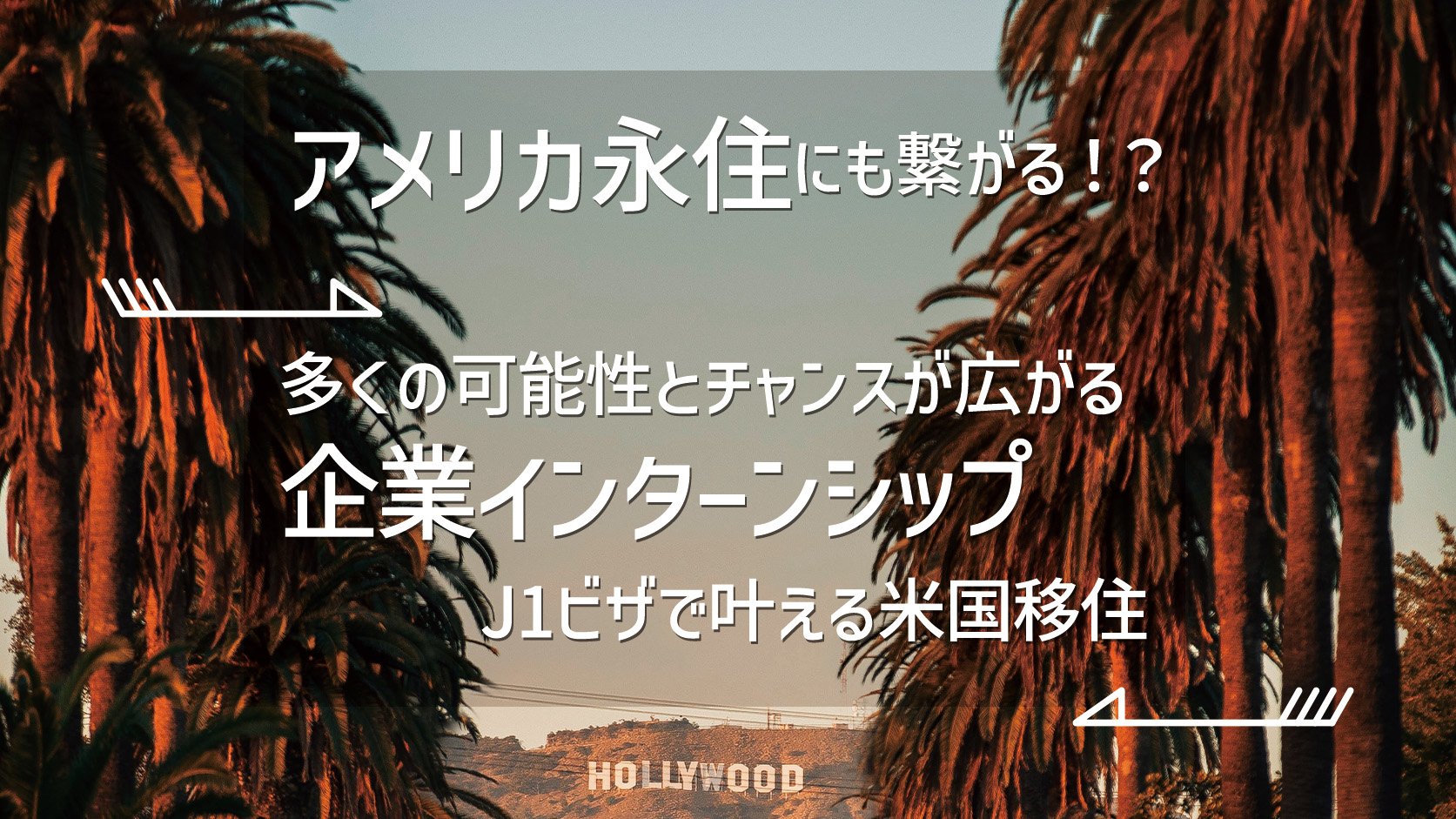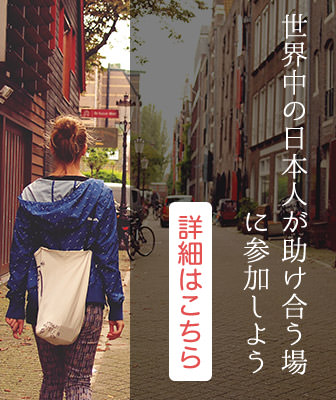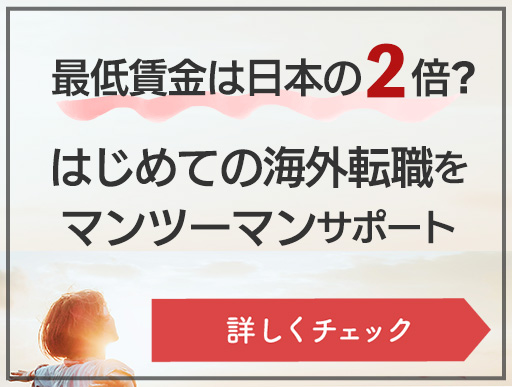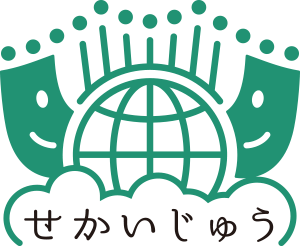海外で子育てをしていると住んでいる地域と日本の違いに戸惑うことがあります。そのうちのひとつが離乳食です。
国によって離乳食の開始時期や食材、考え方も大きく異なるものです。
ここでは、日本とアメリカの離乳食を比較してみました。
アメリカの離乳食の開始時期は生後4ヶ月〜
まず離乳食の開始時期からみていきましょう。
アメリカ:生後4~6ヶ月の間に開始
生後半年までは2ヶ月おきにかかりつけの小児科で健診があるので、4ヶ月健診時に小児科医が離乳食についての案内をします。
離乳食のガイダンスや注意事項を書いた用紙を配布し、相談や質問があれば個人的に対応してくれます。
ミルク以外のものを食べる準備ができているか判断する項目は日本と同じです。赤ちゃんの首が座っている、よだれが増えている、食べ物に興味を示すなどいくつかの条件が揃っていることです。
小児科医から特別な指示がなければ、これらの条件が揃った上で親がタイミングを見計らって開始する家庭が多いです。
アメリカではここ3年ほどは、生後4ヶ月から離乳食を始めるのが主流になりつつあります。
その理由はアレルギー対策です。
食物アレルギー体質の人が多いアメリカでは専門家が研究に取り組んできました。
その結果、離乳食の早期開始がアレルギーになるリスクを減少させるという見解が導き出されています。この新しい研究結果を元に、食材についても従来の考えが随分変わりました。こちらは次のパラグラフで詳しく紹介します。
日本:生後5~6ヶ月の間に開始
生後3~4ヶ月に集団乳児健診を行っている自治体が多く、その時に離乳食指導も行います。
離乳食のガイダンスや注意事項を書いた用紙を配布し、講義形式で保健師が説明していきます。遅くとも生後6ヶ月までには開始する点は日米共通していますね。
離乳食に使う食材の違い
次にそれぞれの国で使われる食材の特徴と違いを比較していきましょう。
国や土地が変われば食文化の違いがあるように、離乳食にもその傾向が見られます。
アメリカ:果物の種類が多く、スーパーフードと呼ばれる食材も取り入れている
ニンジン、リンゴ、サツマイモなど日本でも定番の食材に加え、野菜と果物の種類が豊富です。
タンパク質は鶏肉、ターキー、牛肉が主流で魚は使われません。
またベジタリアン(菜食主義者)の家庭では離乳食もベジタリアンメニューを与えています。ベジタリアンはタンパク質や鉄分が不足しないようにヨーグルトやチーズなどの乳製品や豆類を積極的に食べます。そして鉄分の吸収しやすくするためにビタミンCを多く含む食材も一緒に食べるのです。赤ちゃんの成長に影響が出ないよう、離乳食の栄養バランスにもとても配慮しています。
さらにビーガン(完全菜食主義者)は卵や乳製品も食べないので栄養が偏らないようにサプリメントを与えたり、小児科医や栄養士の指導の下で離乳食を食べさせたりしています。
以下の食材はアメリカの離乳食でよく使われる反面、日本では珍しいものです。
・穀物
ライスシリアル、オートミール
・野菜
アボカド、ビーツ、エンドウ豆、スクアッシュ、ズッキーニ、ケール、ココナッツ、ひよこ豆、レンズ豆
・果物
マンゴー、ブルーベリー、ラズベリー、洋ナシ、プルーン、ザクロ、アプリコット、プラム、
・その他
チアシード、ピーナッツ、キヌア、ターキー、シナモン
また、食物アレルギーを引き起こしやすい食材は元来離乳食では敬遠されていました。
そのため卵、大豆、小麦、ナッツ類、魚、甲殻類は市販のベビーフードには使われていません。
できる限り後に食べさせる方針を取っていたのですが、2010年代後半には逆に早い段階で食べさせる方が良いという考えも出てきました。
しかし、まだ検証が不十分な項目もあるので小児科医や栄養士などの専門家に相談しながら食べさせる必要があります。
日本:タンパク質は魚や大豆製品を多く食べる
日本の離乳食の特徴はなんといっても魚と大豆製品です。
離乳食開始1~2ヶ月目に鯛、カレイ、ヒラメなどの白身魚を与えています。
タンパク質を離乳食の食材として魚を使う国は他にもありますが、日本ほど魚の種類や食事のメニューが多い国は珍しいのではないでしょうか。海に囲まれ魚介類をよく食べる日本ならではの食生活が影響していますね。
そして豆腐、納豆、きなこ、味噌などの大豆製品もよく利用しています。アメリカでは離乳食には推奨されていないので、国によって考え方が異なるのは興味深いですね。
手づくりする?しない?離乳食準備の方針の違い
それでは離乳食はどのように準備しているのでしょうか。
アメリカ:市販のベビーフードを利用する家庭が多い
手軽で合理的な方法を好むアメリカでは市販のベビーフードを利用するのが主流です。
共働きの家庭が多いので、離乳食を作る手間や時間を短縮し、効率よく育児ができるようにしています。
日本ではベビーフードばかり利用していると手抜きだと批判されることもありますが、そんなことはありません。
スーパーに行くと大きな棚にずらりと並んだベビーフードを見ることができるでしょう。
種類が豊富で品質の良いオーガニック製品も発売されています。これは日本よりも早く缶詰や冷凍食品などの保存食が普及していたアメリカの食文化が根底にあるからです。手軽に家庭で調理できる加工食品を食べ、必要な栄養はサプリメントで摂っているという人も珍しくありません。
家庭で手作りする場合も便利な調理グッズを使い、効率よく作ることができます。
食事は実にシンプルで作る品数も1品物が多いです。育児書に食べさせる量の目安はあっても、食べたい子供には欲しいだけ食べさせるという姿勢です。
離乳食の準備は手間をかけずに利用できるものを使い、ストレスを溜めないことが一番だということですね。
日本:従来は手づくりが基本とされてきたが、近年は見直されている
離乳食の作り方やレシピを紹介した本が数多く出版されているように、日本では手作りをしている人が多いです。
十倍粥から始まるゴックン期を経て、モグモグ期、カミカミ期、パックン期まで段階ごとに細かく慎重に進めていきます。
日本は健康意識が高く、育児にも手をかける風潮があります。赤ちゃんのために毎食手作りの離乳食を用意しているのは世界でも珍しいようです。
その一方で、近年は市販のベビーフードに対する考え方も変わってきています。
栄養バランスを考えて作られているので、手づくりでは不足しがちな栄養素も補えます。
そして家庭で作るときに味や食材の固さ、大きさを参考にすることも可能です。利便性と栄養面で優れているので利用する人が増えています。
成長段階ごとの離乳食の進め方
赤ちゃんの成長によって離乳食も徐々に変化していきます。
ここでも手作りする、しないで違いがあります。
アメリカ:月齢が上がってからもペースト状の離乳食
日本と同じようにアメリカも最初は食材をペースト状にしたピューレから始めます。
段階が進むと利用する食材の種類が増え、組み合わせも広がります。しかし、形状を固くすることや固形物の大きさを変化することにはこだわりがないようで、ベビーフードを利用している人は月齢が上がってもペースト状の離乳食を与えています。
ただし、まったく固形物を食べないという訳ではなく、食べ掴みができる頃になると小さく切った果物や、市販の柔らかい食感のおやつも食べています。
日本:月齢に合わせて細かく進める
離乳食の段階を細かいステージに分け進めています。
生後5~6ヶ月はゴックン期、7~8ヶ月はモグモグ期、9~11ヶ月はカミカミ期、12ヶ月以降はパクパク期というように赤ちゃんの発達に合わせて確認しながら食べ物に慣らしていきます。
食べ物の形状もすりつぶしてペースト状にしたものから、徐々に大きさや固さを幼児食に近づけていきます。
ごく普通に実践している方法かもしれませんが、日本のように細やかに離乳食を進めている国は珍しいです。
離乳食の調理法とメニュー
アメリカ:1品料理が多い
前述したようにアメリカの離乳食はシンプルです。
元々アメリカの食事が単品で済ませることも多いので、離乳食にもその影響が出ていると言えます。
最初は粉末状のお米やオートミールを粉ミルクと混ぜたものから始まり、徐々にペーストした果物や野菜を増やしていきます。
食べられる食材が増えると複数のものを組み合わせて味に変化をつけています。
ヨーグルトやチーズなどの乳製品も早い段階で食べさせます。
生後9カ月頃になるとタンパク質が入った食事になり、1歳頃にはマカロニチーズやラビオリパスタなど柔らかい固形の食事が登場します。
日本:主食、主菜、副菜形式
日本は最初におかゆから始め、徐々に食材を増やし、形状も変えていきます。
伝統的な日本食が一汁三菜と言われてきたように、離乳食でも主食、主菜、副菜など一度の食事で複数の料理を用意します。
また、1品の中に色んな食材が使われています。初期から昆布やカツオだしを重視し、味付けにも変化をつけています。
さらには調理法も、煮る、焼く、茹でるなど種類があり、日本人の美味しい食事へのこだわりが離乳食にも反映されているのです。
市販のベビーフードの種類や活用方法
日米共にお店で買えるベビーフードは充実しています。ただし、種類や使い方は離乳食に対する国民性の違いが反映されているようです。
アメリカ:ベビーフードはそのまま与える
合理的で手軽さを好むアメリカでは購入したベビーフードをそのまま食べさせています。
容器は瓶やプラスチック製のものが多く、蓋をあけてスプーンで与えます。直接吸えるパウチタイプもあり、汚さずに外出先でも簡単に食べられるので人気です。
また、ベビーフードにはビタミンや鉄分など不足しがちな成分が含まれています。
科学的に栄養バランスを補っているのがアメリカらしい面白いところですね。
日本:そのまま食べられるものから時短に利用できるものまで豊富
離乳食売り場に行くと大人でも食べたくなるようなバラエティに富んだベビーフードが並んでいます。
瓶詰、プラスチック容器、パウチに入ったベビーフードは段階に応じた形状で栄養バランスを考えて作られているので開封してすぐに食べられます。
また、外出先で食べやすいように使い捨てスプーンがセットになったベビーフードもあります。
そして、手作りする人が手軽に時短で作れるように、粉末やフリーズドライの商品もあります。赤ちゃんの食事は塩分控えめで薄味が基本ですが、味付けのバランスが難しい面も。
だしの旨みや味付けの変化をつけられる粉末ベビーフードはお湯に溶かしたり、作った食事に混ぜるだけでそのような問題を解決できるようにできています。
このように日本のベビーフードはハイクオリティで即座に食べられるものから、手作りを助けるものまで幅広く揃っているのです。
アメリカで子育てするときはどちらの国の方法を取り入れている?
海外で子育てをする日本人は日本の育児書をベースにしつつ、双方の良いところを取り入れてバランスを取っているようです。
離乳食に関しても同様のことが言えます。
離乳食を作るなら日本食が手に入る環境にあるのと、入手しにくい環境でも違います。物流が発達し、昔に比べて海外でも日本の食材が普及したとはいえ、日本で買うよりも高額です。
そのため保存できる食材を一時帰国したときにまとめて購入したり、日本の家族から郵送で送ってもらったりしています。こういう事情のため、自然と住んでいる場所で入手できる食材を使い、工夫しながら離乳食を作ることになります。
また、アメリカの離乳食スタイルをそのまま実施している人もいます。
どちらにも共通しているのは、丁寧で細やかな日本に比べるとアメリカは大らかで良いという意見です。
重要なのはその土地の方法や食材を取り入れて柔軟に対応していくことなのですね。
※離乳食について記載しているウェブサイト
- Centers for Disease Control and Prevention(CDC:アメリカ疾病管理予防センター)
- America Academy of Pediatrics(アメリカ小児科学会)
世界中の日本人が参加する「せかいじゅうサロン」
世界へ広がる海外移住コミュニティ
世界中の日本人同士が繋がり、情報提供したり、チャレンジしたり、互助できるコミュニティ「せかいじゅうサロン」
参加無料。気軽に繋がってください。(2025年6月時点:参加者5800名超えました)
“【特別公開】世界で自由にひとりIT起業”
WEBマーケティングスキルは「世界どこでも働けるワークスタイル」を可能に。
1年で海外居住資金も作れるWEBスキル講座を無料配布中↓